『平安時代編4 地方政治の展開と武士』
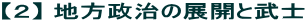 (P.27~28)
(P.27~28)
1 国司の地方支配
基本的語句を正確に覚えることが大切である。
(1)原因
8世紀後半から9世紀は、農民間の格差が拡大して、有力農民も貧窮農民も様々な手段で負担を逃れるようになった。戸籍は重い人頭税がかかる男性を避けて、女性として登録する偽籍が目立つようになり、10世紀になると、戸籍・計帳をもとにして農民から租や調・庸を取り立てて諸国や国家財政を維持することは不可能になった。
そこで政府は国司の交替制度を整備して、任国に赴任する国司の最上席である受領(多くは守)に、大きな権限と責任を負わせるようにした((例外は、親王任国と呼ばれる常陸国・上総国・上野国の3国。親王が守になる(もちろん遙任する)ので、介が受領になる)。
(2)受領の任国経営
受領は、課税対象となる田地を名(みょう)という徴税単位にして、それを有力農民である田堵(後述)に請け負わせて、広さに応じて徴税するようになった。 戸籍・計帳がなければ人頭税は取れないが、そこに田地があれば地代は取れるからである。
徴税を請け負った田堵は、租・調・庸・出挙の利稲を合算した官物(主に米)を納め、雑徭にあたる労役の臨時雑役(手工業品などもあった)を賦課した。田堵の中には、大規模に名を経営をするようになったものを大名田堵という。
「田堵に名の耕作を請け負わせる制度=負名体制」(田堵の中で名の耕作を請負った者を、その名の負名という。)(発展「田堵と負名と名主の違い」へ)
とりあえずのキーワードは
〇「徴税単位=名(名田)」
〇「名を請け負い耕作する有力農民=田堵
〇「大規模経営=大名田堵」
である。
受領は一定額の税を中央に納入する責任を負わせられたが、そのかわりに一国の統治を委ねられるようなった。「国司が徴税請負人化した」と言われる理由である。
受領は、税率を自由に決めることが出来たので、成功(後述)のための財源確保のために高い税率を課す国司は多数にのぼり、11世紀の初めに中央政府は最高税率を規定することとなった。
受領が高い税率を課した背景には、除目(じもく=人事異動)の際に、国家に対する貢献度が勤務評定の基準となったからである。そのため、彼らはその「功」を積むために財政確保を最重視したのである。
そのため、しばしば苛政を行う受領が見られた。その代表が、「尾張国郡司百姓等解」の藤原元命と、「今昔物語集」で「受領ハ倒ル所ニ土ツカメ」と言ったとされる信濃守藤原陳忠である。
受領は、中央から下級官人を郎等(郎党)として率いて任国に下るようになった。郎党たちは元中央官人だから事務能力は高い。受領は、その郎等を強力に指揮しながら徴税を実現していった。また、受領の家子・郎等からなる直属の武士も率いていた。
本来、郡司は徴税や文書作成などの実務を担っており、地方行政に強い力を持っていた。官吏は四等官制なので、国司は4人しかいなかったから、郡司の力が不可欠であった。そのため、郡衙には正税である稲を納める正倉院(正倉は役所の倉庫。多数の正倉があるエリアがあった。
しかし、受領は耕作と貢納を有力農民である田堵に請け負わせて、自ら郎党を指揮してとして徴税を実現していった。そして税は田堵から直接納めさせた。そのため、郡司の力は低下していった。
なお、「尾張国郡司百姓等解」で藤原元命を訴えた百姓も零細で貧しい農民ではない。田堵負名である。実際、百姓たちに受領が殺害されたり、屋敷を焼き討ちされることもあり、収奪する受領も命懸けであった。
【尾張国郡司百姓等解】
藤原元命が尾張守になった986年は、一条天皇が即位した年だった。元命は、式部丞(じょう:3等官)という中央の実務官人としての仕事ぶりが評価されて、京から近い尾張国の受領に任じられたと考えられる。
先に述べたとおり、郡司と一緒になって藤原元命を糾弾した百姓たちは、貧窮農民ではなく、地方の有力者である田堵たちである。郡司や田堵たちは訴状に、「こんなにもひどい負担を課せられた」と訴えているが、彼らは、その「ひどい負担」に堪えられるだけの資力を有していたことも見落としてはならない。
郡司や田堵たちが最も問題視したのは、負担の増加そのものではなく、徴税をはじめとする元命のやり方だったのではないか。元命の手法は、これまで構築されてきた国司と在地の人々との関係形成や、その関係のうえで遂行されてきた方法を全く無視したものであった。郡司たちは、今後も元命のような国司が赴任して、その手法が先例となって定着することを阻止するために上訴したのかもしれないと思う。
ちなみに、上訴によって京に戻された元命に対する朝廷の勤務評価は、「受領として合格」であった。 |
(3)遙任国司
国司が任国に赴任せず、国司としての収入のみを受け取ること(及びそのタイプの国司)を遙任という。受領が郎等たちを率いて任国経営をするので、受領以外はすることがない。そのため受領以外は遙任するようになった。
しかし徴税も田堵がするので、11世紀後半になると、受領も交替の時以外は遙任するようになり、目代という代官を派遣するようになった。
国のトップ(守)が不在(遙任)となった国衙を留守所、留守所をしきる現地の役人を在庁官人という。
基本的にはこれでO.K.だろうが、論述や正誤問題に対応するためにポイントを確認しておきたい。
10世紀に受領が登場する。国司は四等官制だが、受領(守)以外はすることがない。そこで任じられても、どうせすることがないから任国へ赴かない(赴任を免除されている)タイプの遙任がでてくる。(受領とは「解由状を受領する」ところからその名がある。→『平安時代編1 平安初期の政治』参照)
さらに、受領も公領の経営は田堵との契約であったため、それを済ませば任国にいてもこれといってすることもない。そこで、11世紀後半になると、国司交替など限られた時以外は、目代と在庁官人に任せ、普段は在京する者が多くなった。つまり受領も遙任化するわけであり、ここに国司制度は形骸化した。
(4)官職の利権化
①私財を出して朝廷の儀式や造宮・造寺などの費用を請け負う=成功(じょうごう)←「功」(国家への貢献)を「成」す。ぼくのノートでは「私財を提供して官職を得る」と書いているが、私財を提供する場はあくまで朝廷の儀式や造宮・造寺である。
②成功によって同じポストに再任されたり、任期を延長される=重任(ちょうにん)
2 武士の成長
(1)武士の発生
①9世紀から10世紀に地方政治が混乱すると、国司の子孫や地方豪族が武装するようになり各地で紛争が起こるようになる。その鎮圧のために中央から押領使や追捕使が派遣されて、鎮圧後もそのまま残って武士になる者が現われた。
(発展「武士の起源」へ)
(2)武士団の構成
家子と郎等(郎党)の区別(家子は一族、郎等は従者)をしっかり。
(3)天慶の乱
地方武士の反乱であるこの「天慶の乱」(939~941)を一つの項目としたのは、この天慶の乱によって「武士」という身分が誕生したからである。
(かつては「承平・天慶の乱」と呼ばれていたが、朝廷側が反乱だと認識するのは、天慶2年に将門・純友が相次いで国司を襲撃して以降である。それまでは私戦(私的な武力衝突)と見なしていた。そのため、今は平将門の乱と藤原純友の乱を合わせて「天慶の乱」と表記している教科書が多くなったが、「承平・天慶の乱」を使っている教科書もあるので、誤りではない。)
武士の起源には諸説があるが,武士という身分は天慶の乱によって誕生した。9世紀末から10世紀初めにかけて、地方豪族が武装して受領の支配に抵抗するようになった。その取り締まりのために、政府は武芸に優れた中下級貴族を派遣した。現場に到着した中下級貴族は、武装した地方豪族たちを配下に組み入れることで治安を確保した。彼らは「兵(つわもの)」と呼ばれるようになる。
そのようななか、天慶の乱は起こった。これを鎮圧したのが、「兵」たちである。天慶の乱は「地方武士の実力を中央に認識させる契機となった事件」(丸暗記)とされるが、詳しく言うと、私兵を常備する「兵」たちの実力に朝廷が注目し、軍事・警察を請け負わせるようになったのである。
後述するが、平将門を討った平貞盛や藤原秀郷が率いた部下は、彼らの私兵であり、朝廷から与えられたものではない。ここに公権力に武装を公認された「武士」身分が誕生した。
武士は2つのパターンに分かれることになった。
一つは、「京を拠点に活躍して、受領を歴任する=武家(軍事貴族)。例:桓武平氏・清和源氏」
もう一つが、「国衙のもとで受領の国内統治を補完する=地方武士。例:北条氏・三浦氏」である。
「延喜・天暦の治」のど真ん中でおこったこの事件の基本は「誰が、何をして、誰に討たれたか」をセットでおさえることである。
①「平将門は、下総を根拠地として関東で反乱。新皇と称して、平貞盛と藤原秀郷に討たれた。」
②「藤原純友は、瀬戸内海の海賊を率いて、伊予の国府や大宰府を襲撃して、源経基と小野好古に討たれた。」
(実際は、源経基は、純友を討つのに何の役にも立っていない。源経基は、追捕使となった小野好古の副官に任じられたが、純友は源経基が到着する前にすでに小野好古に討たれており、源経基は純友の部下を捕らえただけであった。しかし教科書では源経基が討ったことになっている(山川、東京書籍、第一学習社には好古は載ってもない。その中で清水書院の教科書は「小野好古・源経基によって鎮圧」と好古が先に記されており、素晴らしい)。これは、経基が清和源氏の祖であり、その後の源氏の進出とつなげるためだと考えられるが、ぼくとしては釈然としない)
ちなみに、純友は、もと「伊予国の掾(じょう。国司の3番目)」であったが、「伊予国とは現在でいう何県か」という問いがあった。愛媛県の生徒なのに、千葉県と答えた者もいたが...。
先にも述べたが、この天慶の乱で、「兵の家」(軍事貴族)が成立した。それが平高望を祖とする桓武平氏と、源経基を祖とする清和源氏である。
(4)武士の登用
①都で有力な貴族に奉仕(身辺警護や都の警備)を行う武士の侍という。それで摂関家と深く関係して中級貴族として活躍したのが清和源氏である。
②「滝口の武士」は、似た者3択である。「滝口の武士=宇多天皇→宮中警備」「北面の武士=白河上皇→院の警備(院独自の軍事力)」「西面の武士=後鳥羽上皇」(院政期・執権政治参照)
③他にも検非違使や追捕使や押領使に登用される者もいったが、検非違使の長官(別当)は中央貴族であった。
➃先の受領の項で、「百姓たちに受領が殺害されたり、屋敷を焼き討ちされることもあり、収奪する受領も命懸け」だったので、受領は家子や郎等からなる直属の武士を率いて赴任した(館侍)や、国衙の軍事力として登用される者もいた(国侍)。
(5)刀伊の入寇
ポイントは、九州の武士を指揮して撃退した当時、藤原隆家(当時大宰権帥)と、この事件が起こった1019年は、藤原道長が「この世をば・・・」の歌を詠んだ翌年である。なお刀伊とは、遼の支配下にあった沿海州に住む女真族で、のちに金を建国した。
3 京武者と武家の棟梁
(1) 京都で活動する武士を京武者という。その代表が桓武平氏と清和源氏である。 彼らは京と地元(本拠地)を往還した。中央で有力者などと縁故を結び、その縁故関係を利用して地元での力を蓄えていった。そして、武士団を率いて院や摂関家に仕えるようになり、武士の棟梁になっていった。
(2)桓武平氏は、9世紀の末から東国に土着するようになり、大武士団を形成するようになった。
(3)清和源氏は、10世紀より畿内に本拠を構えて中級貴族として活躍するようになった。
①源経基の子、源満仲は、安和の変に際して源高明を密告して、高明の左遷に貢献したことで、摂関家の侍となった。
②満仲の子である源頼光(酒呑童子を物凄く卑怯な方法で殺したヤツ)は藤原兼家に、頼光の弟頼信は、藤原道長にそれぞれ奉仕した。
③その源頼信が鎮圧したのが、平忠常の乱(1028~1031)である。これが「源氏が東国へ進出する契機」となった。1028年は藤原道長が死去した年であり、この平忠常の乱は摂関政治全盛の時代の出来事だと分かる。
(エピソード「射よ、かれやー貴族の武士観ー」へ)
4 院政期の武士の成長
本当は院政期の項でまとめたかったのだが、紙面の都合でここに入れました。
(1)前九年合戦は、末法元年の前の年(1051)から始まり、後三条天皇が即位する5年前に終わる。言ってみれば藤原頼通の時代の出来事だから、平忠常の乱に続けても良かったのだが、この前九年合戦は次の後三年合戦に繋がっていくのでここに入れました。
陸奥の俘囚安倍頼時の乱を、源頼義・義家父子が清原氏の援助を受け鎮圧」した。
(難問。鎮圧の対象となった安倍頼時は俘囚と呼ばれるが、これは朝廷に服属した蝦夷の意味である。清原氏も奥州藤原氏も俘囚のリーダーを称していた。)
(2)後三年合戦は、源義家が清原氏の内紛を藤原清衡を助けて鎮圧した。
この清原氏の内紛は面白いのだが、キリがないので割愛する。当時、義家は陸奥守であり、鎮圧後、義家は謀反人を討ったので、論功行賞をして欲しいとの文書を朝廷に送ったが、朝廷は義家の私戦として報償はなく、逆に陸奥守を解任された(その後、10年間冷遇された)。そのため義家は、主に関東から出征してきた武士たちに私財から恩賞を出したが、これで義家の名声が高まり、所領を義家に寄進する東国武士が多数出るようになり、義家は武家の棟梁となった。
なお、この事件(後三年の役)の結果、「義家に東国武士からの寄進が集中して、政府があわててこれを禁止した」ことを、正誤問題で問うた大学もあった。(答えは○です)また「後三年合戦図」の金沢の柵の場面(雁の列が乱れるのを見て、伏兵の存在を知る場面)は確認しておきたい。

(3)奥州藤原氏の発展のポイントは
①中心は陸奥の平泉
②奥州藤原氏3代(清衡→基衡→秀衡)は答えられるように。
③陸奥産の金、馬などの産物で繁栄
➃蝦夷や北方の海洋民族との交易をしており、朝廷に直接貢納することができる存在になった。
*のちに源頼朝によって滅亡(1189)させられる。理由は謀反人である源義経を庇ったということになっているが、これはあくまでも名目であり、豊かな経済力、朝廷との友好的な関係が脅威であったからである。
(2005.10.26更新)
(2007.8.16更新)
(2010.3.2改訂)
(2010.8.7加筆)
(2010.9.23一部改訂)
(2013.1.1更新)
(2021.2.1天慶の乱に加筆)
(2025.3.9大幅に修正)
通史目次へ戻る
トップページへ戻る
平安時代編3『摂関政治の確立』へ
平安時代編5『国風文化』へ
